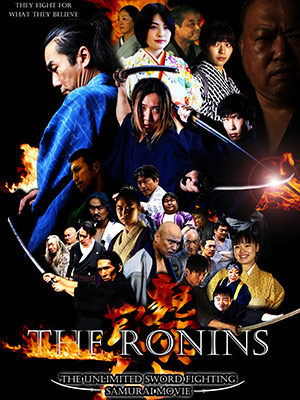開基:藤原鎌足の子・定恵
創建:大宝年間(701~704)
正式名称:一乗山 大法寺
大法寺は天台宗の寺院。古くは大宝寺とも書かれた。「一乗山観院霊宝記」という記録によると、奈良時代の大宝年間に藤原鎌足の子の僧定恵によって開基された寺院。
三重塔(見返りの塔)
国宝指定。1333年大工天王寺四郎某のほか、小番匠七人によって建てられた。塔を良く見ると初重が特に大きいことに気づく、これがこの塔のもっとも大きな特徴であり、形に変化がつき、おちついた形になっている。これは、二重、三重で組物を三手先という最も正規な組み方をしているのに対し、初重だけは少し簡単な二手先にsたので、その分だけ平面が大きくなっている。この手法はこの塔のほか、奈良の興福寺三重塔があるだけできわめて珍しいものである。
また、この塔が建てられれば鎌倉時代から南北朝時代に移る過渡期には、装飾的な彫刻を各所につけるのが、通例であるが、この塔では初重の中央間の一部簡単な物を除いて装飾細部を一切用いていない。しかし、それらに見られる手法は正規な物であって地方的な崩れがまったくみられず、中央の工匠が造営したことが伺える。
大法寺観音堂
国の重要文化財指定。平安中期に建立した。
厨子と須弥檀(国指定重要文化財)
観音堂におかれた厨子で、本尊の十一面観音像を安置してある。時代は鎌倉の末期から南北朝の作という。真反りの軒が強くはね上がり、軒裏の詰組に特徴があり、扉は桟唐戸の禅宗様式の厨子である。また棟の両端に食いついた木彫りの鯱は珍しい例で、日本最古の鯱である。厨子を置く須弥檀は、同時代のもので高欄の束に蓮の彫模様があり、格狭間の形式など鎌倉時代の様式を伝えている。
木造十一面観音立像(国指定重要文化財)
像高171cm、観音堂の本尊で、柱の一本彫りの像は、切株に蓮弁を陰刻した台座の上に立っている。タマゴ形の顔、ふっくらしたほほ、古風で優雅な、859年~876年に流行した量感のあふれる像で、長野県ではもっとも古い仏像である。
木造普賢菩薩立像(国指定重要文化財)
本尊の十一面観世音の脇侍仏で、本尊と同時代にできた仏像と考えられる。像高107cm柱の一本彫り、彫り方、肉付け、衣文等、十一面観音に良く似た仏像である。